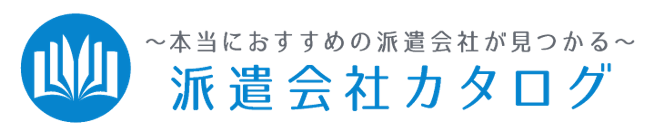これから派遣社員として働く人は、各種社会保険に加入する必要があります。
さらに健康保険に関しては国民の義務なため、雇用形態に関わらず加入義務があります。
派遣社員として働くに当たって、派遣会社で健康保険の加入する場合の条件や契約終了後の保険証をどうするのかについて知っているでしょうか?
派遣社員の保険事情って何かとややこしいですし、意外と知らないコトって多いですよね。
そこで今回は、派遣社員の保険証に関する疑問を解消していきます。
社会保険や健康保険の種類も合わせて、健康保険の加入条件や契約終了後の手続きを解説していきます。
派遣で加入できる社会保険
まず、派遣社員が加入できる社会保険には何があるのでしょうか?
社会保険とは保険料を会社負担にできる保証制度のことをさします。
派遣社員が加入できる社会保険は、具体的には以下の5つの公的保険が含まれています。
- 健康保険
- 労災保険
- 雇用保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
それぞれ、簡単に解説していきます。
健康保険
健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度を指します。
つまり、派遣などの仕事外でのけがや病気、出産などに関しての給付です。
健康保険は、法律で日本国内に住んでいる人が全員加入しなければいけません。
日本人の義務なので、必ず全員加入する必要があります。
労災保険
労災保険とは、雇用されている人が仕事中や通勤途中に起きた出来事が原因のケガや病気、障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。
健康保険との違いは業務中によるケガや病気かそうでないかです。
さらに、療養の費用の自己負担がなく、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっています。

※本ページにはPRが含まれます。
雇用保険
雇用保険とは、日本における雇用保険法に基づいた、失業や雇用継続等に関する保険の制度を指します。
つまり、雇用保険に加入していれば、失業した際に失業給付金を受け取ることができます。
失業給付金としてもらえる金額は働いていたときの給料の額によって異なり、ボーナスは含まれません。
厚生年金保険
厚生年金保険は、労働者やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした保険の制度です。
労働者の老齢や障害、死亡について保険金の給付を行います。
日本政府が運営していて、所得に比例して給付金が変わります。

※本ページにはPRが含まれます。
介護保険
介護保険とは、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした保険制度です。
少子高齢化や核家族化に伴い、家族だけで支えるのは難しいということで、介護が必要な方にたいする給付をします。
介護保険は、40歳になった月から全ての人に支払い義務が生じます。
今の健康保険のチェックしよう

ここからは、日本人の義務である健康保険について解説していきます。
健康保険は働き方や職業によって加入する保険が違います。
派遣会社で健康保険の手続きをする前に、どんな健康保険に加入しているのかを把握しておきましょう。
まず、自分が加入している健康保険をチェックするために、健康保険証の「保険者名称」を確認します。
その保険者名称を確認することで、どの健康保険に加入しているかが分かります。
市区町村の記載は「国民健康保険」
「保険者名称」に市区町村の記載がある保険証は「国民健康保険」に加入しているということです。
国民健康保険は市町村が保険者となって運営しています。
自営業の方や短時間勤務のパートやアルバイト勤務の方、無職の方など、職場の健康保険に加入していない方が基本的に国民健康保険に加入します。
企業名の記載は「組合管掌健康保険」
企業名や業種名、職種名などが書かれている場合は組合管掌健康保険に加入しているということです。
企業が設立する健康保険組合が保険者となって運営しています。
その会社の従業員が加入する保険です。
共済組合
共済組合とは、公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合です。
公務員や私立学校教職員とその家族を対象とします。
共済組合を大まかに分けると、以下のようになります。
- 国家公務員とその扶養者が対象の「国家公務員共済組合」
- 地方公務員とその扶養者が対象の「地方公務員共済組合」
- 私立学校の職員とその扶養者が対象の「私立学校教職員共済」
全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会が保険者として運営しています。
組合健保を設立しない企業の従業員とその扶養者対象とした健康保険です。

どの健康保険でも医療費の自己負担割合などの基本的な制度内容は同じです。ただ、一企業もしくは複数の企業が共同で設立した組合管掌健康保険(組合健保)については「付加給付」という独自の制度のある組合健保もあります。これは被保険者の1ヶ月の自己負担額の上限を定めているもので、例えば上限額が2万5千円だとしたら、医療費がどんなにかかっても1カ月の自己負担の上限は2万5千円となります。また保養施設が格安で利用できるなどの福利厚生サービスが充実している組合もあります。加入している保険でどのようなサービスを受けられるかしっかり確認しましょう。
健康保険の加入手続きは派遣会社がおこなう

健康保険の加入手続きは、派遣先に関わらず、基本的に派遣会社が行います。
しかし派遣会社で健康保険に加入するには条件があります。
その条件に当てはまり、派遣会社で健康保険に加入する人は、以前の健康保険から脱退が必要です。
派遣社員になる前の健康保険が国民健康保険や国民年金だった場合、親や配偶者の保険に被扶養者として加入していた場合は脱退の手続きが必要となります。
脱退手続きは自分でやらないといけません。
派遣会社の健康保険に加入する条件
では、派遣会社の健康保険に加入する条件を紹介していきます。
派遣登録をするだけでなく、実際に企業へ派遣されていなければ社会保険に加入することはできません。
派遣会社で健康保険に加入する条件は「派遣先で働く期間」や「働く時間」によって決まります。
条件は2つのパターンがあり、どちらかの条件に当てはまる場合は派遣会社で健康保険へ加入することになります。
その2つのパターンの条件を紹介していきます。
条件1:フルタイムで働く人
1つ目の条件は以下の通りです。
- 雇用契約期間が2ヵ月以上
- 1ヵ月の所定労働日数が15日以上
- 1週間の所定労働時間が30時間以上
一言でいえば、フルタイムで働く人が条件です。
はじめは2カ月未満の契約だったけど、更新して2カ月以上継続して働くことになったという場合は更新の時点から加入できます。
条件2:フルタイムではないが長期間働く人
2つ目の条件は以下の通りです。
・1年以上の雇用見込みがある
・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・1ヵ月の賃金が88,000円以上である
・会社の従業員数が501人以上である
1年以上働く予定であれば、フルタイムではない人でも加入できます。
条件に満たない場合は国民健康保険に加入
健康保険に加入する条件を満たしていない派遣社員の場合、個人で国民健康保険加入の手続きを行う必要があります。
国民健康保険の加入手続きは住民票のある市区町村役場で可能です。
国民健康保険への加入手続きは勤めていた会社を離職してから14日以内に行わないといけません。
派遣会社で健康保険に加入できないとわかったら早めに手続きをしましょう。

派遣会社で健康保険に加入する条件に「雇用契約期間が2ヵ月以上」というのがあります。お仕事の紹介を受けた時に派遣先での契約期間が「長期」が前提となっていても、初回契約時の契約期間については「1ヵ月」としている場合が少なくありません。そして契約更新時から次の契約期間を「3ヵ月」としたりするケースが多いようです。そのため、このような場合は最初の1ヵ月は一時的でも国民健康保険などの加入が必要となる可能性があります。扶養認定制度のない国民健康保険の場合、扶養家族が多いと保険料の負担が重くなることがあります。始めから派遣会社での健康保険に加入したいような場合、初回契約時の契約期間が「2ヵ月」以上かどうかも確認しましょう。
契約が終了したら保険証は返却する
保険証は、現在就業中の派遣会社との契約が終了した時点で派遣会社に返却することになります。
退職日から5日以内が返却期限なるので、早めの返却を心がけましょう。
次に就業する派遣会社で、新たにその派遣会社の社会保険に加入する手続を行われ、新しい保険証が支給されます。
不正使用はやめよう
資格が無効になった後に保険証を使用した場合は、不正使用となります。
保険証を誤って使った場合は、総医療費の7割から9割を返納金として、健康保険証に記載の保険者に返還しないといけません。
個人で高額な医療費を負担することになるので、不正使用に注意しましょう。
無保険に気を付けよう
健康保険に加入していない「無保険」の状態に気を付けましょう。
健康保険と年金保険の加入は国民の義務なので、どんな時も必ず加入しないといけません。
例え、次の仕事が2カ月先に決まっているとしても、すぐに加入しないといけない訳です。
結局、「無保険」は過去にさかのぼって保険料をしっかり請求されます。
余計に保険料を支払わなければならない可能性もあるので、注意しましょう。
契約終了後の健康保険は?
派遣契約が満了となり、失業者となった際、健康保険に対して、どのような対応をするべきでしょうか?
以下の3通りの方法があります。
・自分で国民健康保険に加入
・任意継続手続を行う
・家族の扶養に入る
それぞれ、解説していきます。
自分で国民健康保険に加入
まず、自分で国民健康保険に加入するという方法があります。
派遣会社で介入していた健康保険から国民健康保険へ切り替えるということです。
派遣会社の契約終了日の翌日から14日以内に手続きを行わなければいけません。
国民健康保険は傷病手当金の支給はないですが、出産育児一時金の支給があります。
各市区町村の役所で手続きを行いましょう。
任意継続手続を行う
健康保険は任意継続をすることも可能です。
派遣会社の契約終了日の翌日から、20日以内に申請しないといけません。
期限を過ぎた場合は、任意継続の手続きはできないので注意が必要です。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を協会けんぽなどの団体に提出して、継続できます。
任意継続は最長で2年間の継続が可能です。
派遣会社である事業主と折半していた分の保険料も負担することになるので、国民健康保険に加入した方が、保険料が安くなる可能性もあります。
家族の扶養に入る
家族の扶養に入るという方法もあります。
家族・親族が勤務をしている会社の健康保険に扶養として入るということです。
就労している企業の健康保険が適用されます。
詳しい保険内容については企業によって違う可能性があるので、自分で調べてみましょう。
派遣社員の保険証に関する疑問を解消!健康保険の加入条件や契約終了後の手続きを解説!まとめ
ということで健康保険の加入条件や契約終了後の手続きを解説してきました。
派遣で働く場合の社会保険は労働時間と契約期間によって加入条件が異なることが分かりましたね。
転職や退職、契約満了を控えている方は、辞めた後に健康保険の切り替えを自分で行う必要があるので、国民健康保険や任意継続の方法を理解しておくと安心ですね。
健康保険に限らず、保険に関する知識は人生において大切なので、今後もしっかり整理しましょう。