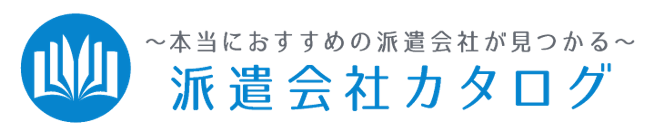派遣社員で働いている方で、派遣でも長期休暇を取得したい!と思いますよね。
結論からいうと、派遣社員でも正社員と同様に長期休暇を取得することができます。
ただ、取得する際には注意しなくてはいけないこともあるのです。
今回は、派遣社員が長期休暇を取得する際に気をつけなくてはいけないポイントと、申請する際の流れについて詳しく解説していきます!
長期休暇取得に必要な派遣の”有給”の定義
みなさんは有給とは何か、ご存知ですか?
有給を使って休めるということはわかっているけど、いつもらえるのかはわからないという方も多いのではないでしょうか?
有給とは法律で定められているもので、以下のように記載されています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
(参照:e-gov法令検索)
派遣だから適用されないのではないかと思うかもしれませんが、この法律は正社員だけではなく派遣もアルバイトもすべての労働者に適用されます。
取得する際には、派遣先の担当者と派遣会社の両方に休暇を取る旨を伝える必要があります。

何日前までに申請するかなど、ルールは派遣会社によって異なるので確認しておきましょう!
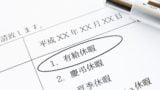
※本ページにはPRが含まれます。
長期休暇を取得する際の注意点

長期休暇を取得する際の注意点を紹介いたします。
注意点を知らずに長期休暇を申請してしまうと、トラブルや契約更新にも関わってきますので、しっかり確認してください。
繁忙期を考慮する
会社が忙しくなる繁忙期に長期休みを取得するのは、周囲に負担がかかってしまいますよね。
ただでさえ仕事量が多い繁忙期に休んだ人の分まで仕事が増えてしまうのは、周囲の人からすると迷惑です。
会社側からすると、繁忙期こそ働いてほしいと考えています。
派遣社員は契約をして働いているため、自分の都合だけで繁忙期に長期休暇を取得して業務に支障をきたすと、次の契約更新にも関わってくるので注意が必要です。
自分の仕事は終わらせる
長期休暇を取得する前に、自分に任されている仕事は終わらせておくようにしましょう。
自分に任された仕事を、長期休暇を取得するからといって他の人に押し付けてしまっては周りの人はよく思わないですよね。
もしも終らない場合には、早めに申告して引き継ぐようにしてください。
自分の仕事が終わっていないのに、報告もせず長期休暇に入ってしまうと仕事が滞ってしまい会社に迷惑をかけてしまいます。
長期休暇の間も周りの人が困らないように、長期休暇の前に対策をしておきましょう。
時期がわかっている場合には早めに申請する
旅行などあらかじめ長期休暇を取得する時期がわかっている場合には、早めに申請をしましょう。
直前だと仕事の都合がつかず許可してもらえない可能性が高まります。
予定がわかっている場合には、少なくとも1ヶ月前には申請してください。
早めに申請することにより、会社側の都合をつけやすいだけではなく、自分も仕事の予定をたてやすくなるため双方にとってメリットがあります。
病気やケガでの長期休暇には注意
病気やケガは旅行での長期休暇とは違い、予測ができませんよね。
法律では有給が発生するのは就業してから半年後と決まっています。
法律では半年後と決められていますが、会社によっては就業日から発生したり、3か月後に発生したりする場合もありますので、有給のルールを確認してみてください。
有給が発生する前に休んでしまうと無給扱いになってしまいます。
無給扱いになると給与が減ってしまうので、特にひとり暮らしの方にはタメージが大きいです。
有給が発生していたとしても、日数は限られているため休みが長期すぎると有給もなくなってしまいますよね。
無給では生活ができなくなってしまいますし、長期の休暇は契約が打ち切られる可能性もあります。
そのため、病気やケガなど万が一のために備えておくことが大切です。
以下の方法を日ごろから考えておくようにしましょう。
- 社会保険に加入する
- プラスで就業不能保険に加入する
- 貯金をしておく
社会保険に加入する
社会保険は、万が一に備えられる公的保険制度です。
社会保険の中にも種類があり、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つがあります。
派遣社員でも正社員と同様に、条件を満たしていれば加入することが可能です。
まずは加入条件に付いて説明していきます。
労災保険は労働者であればだれでも自動的に被保険者となります。
雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる方が対象です。
健康保険、介護保険、厚生年金保険については以下の条件をすべて満たす方が対象になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 契約期間が1年以上の見込み
- 賃金が月8.8万円以上
- 学生ではない
保険の加入条件を満たすことができる働き方をすることがおすすめです。
ただ、保険に加入すると月々保険料がかかり、給与から天引きされていきます。
保険に加入することで保証は手厚くなり安心できますが、保険料を支払うことがいやだという方は、条件を超えない範囲で働くようにしましょう。
続いては保険ごとの特徴を紹介していきます!
健康保険
健康保険は最も使われているもので、病気やケガの医療負担を抑えることが可能です。
また、出産一時金や、出産で会社を休んだ際に会社から手当をもらえなかった場合に手当金が支給されます。
通院や出産にはお金がかかるので、一時金や手当がもらえることはとても助かりますよね。
介護保険
40歳以上の方は、介護サービスを原則1割負担で受けることが可能です。
ただし、前年度の所得によって2割か3割になることもあります。
40歳から64歳までの方は、指定されている16疾病によって介護認定を受けた場合に対象となります。
サービスを受けられる対象者の幅は狭いですが、もし病気になってしまった時には役に立つ保険です。
厚生年金保険
老後の生活を保障する老齢年金で、国民年金に上乗せして給付される年金です。
病気やケカなどで障害が残った時の障害年金や、被保険者が亡くなったときに遺族に支払われる遺族年金などをいいます。
保険料は、毎年4月から6月に支払われる給与を計算した金額と、ボーナスに対して共通の保険料率を掛けて算出しています。
支給される保険料は個人によって違うので一概にいくらということはできません。
厚生年金に加入していた長さと、払ってきた保険料の額によって決まります。
将来的に生活が厳しくなったときに備える保険です。
雇用保険
雇用保険は、失業してしまった場合や、雇用の継続が困難となる場合に保証を受けることができます。
失業保険を受給している人が再就職したときにも手当を受け取ることが可能です。
手当を受けるためには、離職前の2年間で雇用保険の加入期間が通算で12か月以上あることが必須条件になります。
また、働く意思があるという前提で受けられる保険なので、手当を受ける場合には求職活動をしなくてはいけません。
保証を受けるためにやらなくてはいけないことが多いかもしれませんが、派遣社員の場合には、契約期間が決まっていますし、働けなくなることも考えられますので入っておくと安心できますね。
労災保険
業務上と、通勤途中の事故によって病気やケガをした場合に、本人や遺族に保険金が給付されます。
特に通勤途中で事故にあった場合には労災保険が役立ちます。
労災保険は全額事業主が負担するものです。
派遣スタッフの場合は派遣会社が負担してくれています。
先程も述べた通り、加入条件もなく自動的に加入するものなので、もしも業務上と通勤途中で事故にあった場合には利用しましょう。
プラスで就業不能保険に加入する
保険に入りたいけど、勤務日数が条件に足りていないから公的保険に入れない…という方、公的保険だけでは不安だからもっと保険を手厚くしたい…という方には、民間の保険に加入することをおすすめします!
民間の保険会社から、就業不能になった場合の保険が出されていることをご存知でしたか?
民間の保険会社ですので、種類も豊富で自分に合った保険に加入することができます。
派遣会社によっては団体で保険に入れる場合もあり、その場合には団体割引が適用されるので、加入を検討している場合には派遣会社に確認してみましょう。
貯金をしておく
民間保険の加入には月々保険料がかかります。
その負担が難しい場合には日ごろから貯金をしておきましょう。
今は働くことができていたとしても、いつ働けなくなってしまうかは誰にもわかりません。
働けなくなってしまった時のことも考えて、毎月の給料を使い切ってしまうのではなく、貯金をしておくようにしましょう。
派遣が長期休暇を取得する場合の申請方法

派遣でも長期休暇が取得できることがわかり、実際に長期休暇を取得しよう!と思った方もいらっしゃいますよね。
しかし、長期休暇を取得するには申請が必要です。

ここからは長期休暇を取得する際の申請方法について、詳しく紹介していきます!
①派遣会社へ相談
派遣社員が長期休暇を取得する場合には、派遣会社と派遣先両方の許可が必要です。
まずは派遣会社へ先に相談をしましょう。
会社によって長期休暇が取得できないという場合もありますし、長期休暇を取れる時期や日数があらかじめ決まっている場合もあります。
派遣会社が派遣先ごとのルールを認識していますので、派遣先とのトラブル防止のためにもまずは派遣会社に相談しましょう。
その場合には、長期休暇を取得したい理由を具体的に説明してください。
②派遣先へ相談
派遣会社に相談し、許可をもらった後で派遣先に相談しましょう。
派遣会社と同様に取得する理由を具体的に説明してください。
業務についても、自分の仕事を終わらせることができるのか、終わらない場合には引き継ぎできるのかを報告します。
先の予定でわからないという場合にも、わかる範囲でいいので報告をしましょう。
長期休みを取得しやすいのは大企業・短期の仕事
会社によっては、長期休みを申請しづらい、誰も取得していないので言いづらいという場合もありますよね。
それでも長期休暇を取得したい!というのであれば、最初から休みを取得しやすい職種に応募することも手段の一つです。
大企業の場合
厚生労働省の調査では、企業の規模が多いほど年間休日の総数も多いというデータがあります。
企業によっては、必ず長期休暇を取得すると義務付けられている企業もあるほどです。
会社で義務付けられていると、労働者からすると申請しやすいですよね。
製造業の場合
製造業では、祝日に出勤するかわりにお盆やお正月に長期連休を設定している会社が多いです。
製造業は機械の保守点検を行わなくてはいけません。
保守点検のためには機械を止める必要があり、そのためには長期で稼働を止めたほうが会社側の都合がいいです。
計画生産もできるため、製造業では長期休暇を取得しやすいです。
しかし、保守点検に関わる仕事や、食品など賞味期限が短いものに関しては製造業でも休みを取れないことが多いので気をつけてください。
学校関連の事務
年間休日ではなく、長期休暇の取りやすさという意味では学校事務もおすすめです!
学校は生徒に長期休みがあるため、生徒の長期休みの間は事務も休みになる場合があります。
休みとは決められていなくても、長期休暇が認められやすいです。

※本ページにはPRが含まれます。
短期の仕事
派遣の求人には、3か月未満の短期の仕事も多くあります。
一つの企業で有給を使用して長期休暇を取得するのではなく、短期の派遣を上手に利用することも長期休暇を取得できる方法のひとつです。
自分の休みたいときに自由に休むことができますし、仕事とプライベートのメリハリがつきます。
これは派遣だからこそできる働き方です。
自分の趣味の為、夢の為に好きな時に長期で休みたいという方は、派遣社員として短期で働いていくことをおすすめします。
長期休暇を取得してメリハリのある働き方を!
派遣社員も長期休暇を取得することができますし、短期の派遣として働いてメリハリをつけて働くこともできます。
しかし万が一のことは誰にでも起こりうることですから、保険に加入したり、貯金をしておいたり、備えておくことも大切です。

長期休暇を利用して、息抜きをしながら上手に働きましょう!